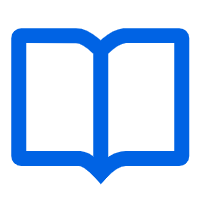日本哲学哪个大学强?
京都大学是原日本帝国大学的四大校区之一,也是战后恢复帝国大学制度时的四个校区之一(东京大学和横浜国立大学也是);这四个校区分别主管三个专业方向——京都大学以人文科学和自然科学见长,东京大学以理工见长,横浜国立大学以法律和经济见长,而神户大学则以文学和理学见长。
因此按照惯例,我们一般把上述四所学校称为“旧帝大”,而将战后新成立的东大、京大、东北大等称作“新帝大”。 当然,现在“旧帝大”这个称呼已经变成京都大学的专属名词了,因为其他三所都已经改制为综合性的大学。
而在二战之前,除了作为教育机关的学术地位之外,京都大学还有一个重要的身份——国立研究所的所在地。这里所说的“国立研究所”并不是我们平时所理解的做研究的机构,而是指那些国家设置的研究机构,这些研究机构除了一部分是由中央政府设立外,相当一部分是以“国立研究所”的名义由各个省厅设立。 而当时被叫做“中央研究所(せんちゅうけんきょうしょ)”的这个机构,也就是现在的国立科学振兴研究所,它在战前是以农、林、矿业三个方面为主进行研究活动的。
而京都大学所处的地理位置恰好非常适合这种大规模的研究所的建设——京都比邻濑田川,拥有大量可用水力发电的资源;而京都平原土地广阔,且处于日本列岛的中部,交通便利,易于运输。在1930年代初期,在日本经济高度成长期到来之前,京都便成为“国立研究所”建设的重点城市。
神戸にある国立研究所の建設をめぐってもといわれる。この所には、理化学研究所、工科大学、農学部があった。 理化学研究所は一九三七年三月成立した。本部となったのは、現在の第一研究所と呼ばれている。第一研究所は、物理、化学科をまずおき、次に生物、材料学科をさかのぼり、工学を総合すべく配置していった。「原子力の研究」という目的を掲げ、核融合の開発に全力をつとめた。
二戦後、アルゲニット法を运用して原爆試験を実施すべく準備していた。この時期は中島哲郎教師が所長を務めていた。 中島教師によると、神戸に設けられた研究所は「帝国大学校時代に比べると、研究の活動に必要な人材を十分に取り込むことができない。その原因は多角化と分散化の傾向だ」と分析されている。 一方、農学部は一九五四年九月建立された。本所が神戸市東滩区にある為、西滩の农田を利用して「農業実験場」(现 神戸市立農林博物館)としている。